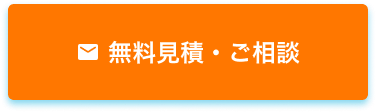目次
固定電話・電話回線に関する
お悩み・ご相談はお気軽に!
お客様の様々なニーズにお応えし、
ご利用に合う最適なプランをご提案します。
はじめに:なぜ今、「固定電話の廃止」が経営課題なのか?
現代のビジネス環境において、「会社の固定電話を廃止するかどうか」という問いは、単なるコスト削減の議論を超え、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)と働き方の未来を左右する重要な経営課題となっています。かつては企業の「顔」であり、社会的信用の証とされた固定電話ですが、テクノロジーの進化と社会の変化という二つの大きな波によって、その役割は根本から見直され始めています。
一方では、スマートフォンの爆発的な普及とクラウドサービスの成熟があります。従業員一人ひとりが高性能な通信デバイスを常に携帯し、インターネットさえあればどこでもオフィス環境を再現できる時代になりました。これにより、コミュニケーションは物理的な「場所」に縛られることなく、より柔軟で即時性の高いものへと変化しています。
もう一方では、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に加速した、テレワークやハイブリッドワークといった新しい働き方の定着です。国内企業の99%を占める中小企業においても、事業継続計画(BCP)の観点や、多様な人材を確保するための魅力的な労働環境提供の観点から、場所を選ばない働き方への対応は避けて通れないテーマとなっています。この文脈において、オフィスに物理的に設置された固定電話は、従業員の出社を強制し、柔軟な働き方を阻害するボトルネックとなりかねません。
このように、固定電話の存廃問題は、単なる通信インフラの選択ではなく、企業の競争力、生産性、そして未来への適応力を測るリトマス試験紙となりつつあります。この決断は、企業のデジタル成熟度を示し、変化に対応できる俊敏性を持つ組織であるかどうかの指標とも言えるでしょう。
本記事では、中小企業の経営者や総務・IT担当者の皆様がこの重要な意思決定を下すために、総務省などの公的データを基に「固定電話廃止」の現状を客観的に分析します。その上で、メリット・デメリットを徹底比較し、クラウドPBXをはじめとする代替ソリューションを具体的に解説します。そして、失敗しないための移行手順までを網羅した「完全ガイド」として、貴社の未来を切り拓くための一助となる情報を提供します。
【参考サイト】https://www.konicaminolta.jp/business/solution/idea-showroom/detail/ejikan/column/introduction-to-smes/index.html
データで見る「固定電話」の現状:減少する契約数とスマートフォンの普及
「固定電話はもはや時代遅れ」という感覚は、多くの人が肌で感じていることかもしれませんが、その実態を公的なデータで確認することで、この変化が一時的なトレンドではなく、不可逆的な社会全体の構造変化であることが明確になります。ここでは、総務省が発表している統計データを基に、固定電話の現状を客観的に見ていきましょう。
総務省の「情報通信白書」によると、固定電話の契約数は一貫して減少し続けています。固定通信(NTT東西加入電話、直収電話、CATV電話など)の契約数は年々減少傾向にある一方で、移動通信(携帯電話など)の契約数は堅調な伸びを示しています。その差は歴然としており、移動通信の契約数は、固定通信の契約数の約11.4倍にも達しています。2020年度末時点で、固定電話の契約数が5,284万件であるのに対し、移動電話の契約数は1億9,512万件と、その差は圧倒的です。この数字は、日本の通信インフラの主役が完全に固定電話から携帯電話へと移行したことを示しています。
この移動通信の普及を牽引しているのが、言うまでもなくスマートフォンです。NTTドコモ モバイル社会研究所の調査によれば、携帯電話所有者に占めるスマートフォンの比率は、2010年にはわずか4%でしたが、2015年に5割を超え、2021年には9割を突破。そして2024年には97%に達するという驚異的なスピードで普及しました。
総務省の「通信利用動向調査」でもこの傾向は裏付けられており、世帯におけるスマートフォンの保有割合は90%を超えています。一方で、かつては家庭の必需品であった固定電話を保有している世帯の割合は減少し続けており、令和5年の調査では57.9%となっています。もはやスマートフォンは「一家に一台」ではなく「一人に一台」が当たり前の時代であり、個人のインターネット利用機器としてもパソコンを大きく上回り、20代から59歳の各年齢階層では9割以上がスマートフォンを利用している状況です。
これらのデータが示す本質的な変化は、人々のコミュニケーション様式が「場所(Place)」中心から「個人(Person)」中心へと根本的にシフトしたことです。かつては「会社の事務所にかける」「自宅にかける」というように、特定の場所にある電話機を呼び出すのが一般的でした。しかし、今や人々は特定の個人に直接連絡を取ることを期待しています。その相手がオフィスにいようと、自宅にいようと、移動中であろうと関係ありません。
この現代のコミュニケーションの常識に対して、物理的な場所に縛られる従来の固定電話システムは、構造的にミスマッチを起こしています。顧客や取引先、そして自社の従業員に対して、時代遅れのコミュニケーションを強いることは、ビジネスチャンスの損失や生産性の低下、さらには「変化に対応できない企業」というネガティブな印象につながりかねません。データは、市場や社会がすでに「個人」中心のコミュニケーションへと移行したことを明確に示しており、企業もこの流れに適応していくことが求められています。
【参考サイト】https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd242210.html
【参考サイト】https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/250530_1.pdf
中小企業が固定電話を廃止するメリット・デメリット徹底比較
固定電話の廃止は、中小企業にとって大きな変化です。導入を検討する際には、コスト削減や業務効率化といった魅力的なメリットだけでなく、社会的信用や業務上の注意点といったデメリットも正確に理解し、総合的に判断する必要があります。ここでは、中小企業の視点からメリットとデメリットを徹底的に比較・分析し、それぞれの対策についても解説します。
メリット:コスト削減と業務効率化の実現
固定電話を廃止することで得られるメリットは多岐にわたりますが、特に「コスト削減」と「業務効率化」のインパクトは絶大です。
コスト削減
最も直接的で分かりやすいメリットが、通信コストの大幅な削減です。
- 機器・回線コストの撤廃: 従来のビジネスフォンシステムでは、PBX(電話交換機)と呼ばれる主装置の購入やリースに数十万円から数百万円の初期投資が必要でした。加えて、定期的なメンテナンス費用や、故障時の修理・交換費用も発生します。固定電話を廃止すれば、これらの機器コストが一切不要になります。
- 基本料金・工事費の削減: 固定電話回線の月額基本料金や、オフィスの移転・レイアウト変更のたびに発生する配線工事費も不要になります。これらの固定費を削減できることは、キャッシュフローの改善に直結します。
- 通話料の最適化: クラウドPBXなどの代替サービスを導入すれば、拠点間や従業員同士の通話を無料の内線扱いにでき、外線通話料も全国一律の安価な料金体系になることが多く、全体の通話コストを圧縮できます。
働き方の多様化
固定電話の廃止は、現代的な働き方を実現するための基盤となります。
- テレワークの完全実現: 固定電話がある限り、「電話番」のために誰かが出社しなければならないという問題が発生します。固定電話をなくし、スマートフォンやPCで会社の代表番号宛の電話を受けられるようにすれば、この制約がなくなり、全社的なテレワークやハイブリッドワークへの移行がスムーズになります。これは、優秀な人材の確保や従業員満足度の向上にも繋がる重要な要素です。
- BCP(事業継続計画)対策: 地震や台風などの自然災害、あるいはパンデミックによってオフィスへの出社が困難になった場合でも、従業員が自宅や別の場所で電話業務を継続できます。これにより、事業の停滞リスクを大幅に軽減できます。
業務効率の向上
日々の業務における非効率な作業を削減し、生産性を高めます。
- 電話取次ぎ業務の撲滅: 「〇〇さん、お電話です」という内線取次ぎは、電話を受けた従業員と本来の担当者の双方の業務を中断させ、生産性を低下させる大きな要因です。クラウドPBXなどを利用すれば、担当者のスマートフォンに直接着信させることができるため、この無駄な取次ぎ業務がゼロになります。伝言ミスによるトラブルも防ぐことができます。
- 機会損失の防止: 担当者が外出中や会議中でも、自身のスマートフォンで直接電話を受けられるため、「担当者不在」によるビジネスチャンスの損失を防ぎます。顧客からの問い合わせに迅速に対応できることは、顧客満足度の向上にも直結します。
オフィスの最適化
物理的な制約から解放され、より柔軟なオフィス環境を構築できます。
- レイアウトの自由化: 電話線の配線を気にする必要がなくなるため、オフィスのレイアウト変更が容易になります。フリーアドレス制やABW(Activity Based Working)といった、従業員が自由に働く場所を選べる先進的なオフィス環境の導入もスムーズです。
- 省スペース化と移転の容易さ: PBX装置や大量の電話機がなくなることで、オフィススペースを有効活用できます。また、将来的なオフィス移転の際も、大掛かりな電話工事が不要なため、移転にかかるコストと時間を大幅に削減できます。
デメリット:社会的信用と業務上の注意点
一方で、固定電話の廃止には慎重に検討すべきデメリットや注意点も存在します。ただし、これらの多くは後述する代替ソリューションによって解決可能です。
社会的信用の低下懸念
特に伝統的な業界やBtoB取引において、依然として根強く残る懸念点です。
- 市外局番の持つ信頼性: 「03」や「06」といった市外局番から始まる電話番号は、その地域に事業所が実在することの証明となり、企業の信頼性を示す要素の一つと見なされてきました。連絡先が携帯電話番号のみの場合、特に新規取引の際に「事業の実態が不明確」「すぐに連絡が取れなくなりそう」といった不安感を与える可能性があります。
- 顧客層による印象の違い: 高齢者層を顧客に持つビジネスや、地域に根差した事業の場合、馴染みのある固定電話番号がないことに戸惑いや不信感を抱かれるケースも考えられます。
金融機関・公的手続きへの影響
実務上、問題となりうるケースです。
- 法人口座の開設や融資審査: 一部の金融機関では、法人口座の開設や融資の申し込み時に、固定電話番号の記載を求められることがあります。これは、事業の実在性を確認する審査項目の一つとなっているためです。携帯電話番号だけでは審査が通りにくくなる可能性が指摘されています。
- 各種許認可・補助金の申請: 業種によっては、許認可の申請や補助金・助成金の申請書類に固定電話番号が必要となる場合があります。
FAX利用の問題
日本の中小企業にとって、今なお無視できない業務プロセスです。
- 物理的なFAX機が使用不可に: 従来のFAX機は固定電話回線を利用して送受信するため、回線を解約すると使用できなくなります。官公庁や特定の業界の取引先との間で、依然としてFAXでのやり取りが主流である場合、業務に支障をきたす可能性があります。
災害・停電時の通信確保
事業継続の観点から重要なポイントです。
- 停電時の可用性: 従来の固定電話(アナログ回線)は、電話局から電話線を通じて電力が供給されるため、オフィスが停電しても通話できる場合があります。一方、IP電話やクラウドPBXは、ルーターやPC、スマートフォンなど、オフィスや自宅の電源とインターネット接続に依存するため、停電やネット障害が発生すると利用できなくなります。災害時の重要な連絡手段としての信頼性には差があると言えます。
これらのメリット・デメリットを正しく理解することが、最適な判断への第一歩です。次の表は、これまでの議論をまとめたものです。特に注目すべきは、「デメリット」の多くに「対策・解決策」が存在する点です。これは、固定電話廃止における課題が、技術の進歩によって乗り越え可能な「移行期の挑戦」であることを示唆しています。
| カテゴリ | メリット | デメリット | 対策・解決策 |
|---|---|---|---|
| コスト | 機器(PBX)・回線・維持費を大幅に削減できる。移転やレイアウト変更時の工事費も不要。 | 従業員の携帯電話を業務利用する場合、通話料が増加する可能性がある。 | クラウドPBXを導入し、スマートフォンを内線化する。法人向けのかけ放題プランを活用する。 |
| 業務効率 | 電話取次ぎ業務が撲滅され、従業員が本来の業務に集中できる。テレワークや多様な働き方を推進できる。 | 担当者が応答できない場合の対応が不明確になりがち。 | クラウドPBXのグループ着信機能やIVR(自動音声応答)を活用し、チームで対応できる体制を構築する。 |
| 社会的信用 | - | 連絡先が携帯電話番号のみだと、企業の信頼性が低いと見なされる場合がある。金融機関の手続きで不利になる可能性。 | 「番号ポータビリティ制度」を利用し、既存の市外局番付き電話番号をクラウドPBXで引き継いで使用する。 |
| 事業継続(BCP) | 災害時でも従業員が場所に縛られず電話業務を継続できる。 | 停電やインターネット回線の障害が発生すると通話不能になる。 | 携帯電話回線への自動切り替え機能を持つサービスを選ぶ。災害用伝言ダイヤル(171)など代替連絡手段を確保しておく。 |
| その他 | 電話機や配線がなくなり、オフィスが省スペース化され、レイアウトの自由度が向上する。 | 従来のFAX機が利用できなくなる。 | 「インターネットFAX」サービスへ移行し、PCやスマートフォンでFAXを送受信する。 |
この比較からわかるように、固定電話を廃止する際の課題は「固定電話を維持し続ける」ことではなく、「固定電話が担ってきた機能(信頼性のある番号、FAXなど)を、いかにしてより効率的で柔軟な新しいテクノロジーに移行させるか」という点に集約されます。この視点を持つことで、デメリットを恐れるのではなく、積極的に未来の働き方を設計することが可能になります。
【参考サイト】https://business.ntt-east.co.jp/content/denwa/tel_column/land-line_reason/
固定電話・電話回線に関する
お悩み・ご相談はお気軽に!
お客様の様々なニーズにお応えし、
ご利用に合う最適なプランをご提案します。
固定電話に代わる次世代の電話ソリューション
固定電話を廃止すると決めた場合、その代替となるコミュニケーションツールを導入する必要があります。現代には、それぞれに特徴を持つ多様なソリューションが存在します。自社の業務内容やコミュニケーションのスタイルに合わせて、これらのツールを単体、あるいは組み合わせて利用することが、円滑な移行の鍵となります。
クラウドPBX (Cloud PBX)
固定電話廃止を検討する中小企業にとって、最も有力かつ総合的な解決策となるのがクラウドPBXです。これは、従来オフィス内に設置していたPBX(電話交換機)の機能を、インターネット上のクラウドサーバーで提供するサービスです。
- 仕組み: 従業員は、専用アプリをインストールしたスマートフォンやPCを使い、インターネット経由でクラウド上のPBXに接続します。これにより、個人のデバイスが会社のビジネスフォンとして機能するようになります。
- 主な機能: 会社の代表番号での発着信 従業員間の無料内線通話 不在時の自動転送、グループ着信 IVR(自動音声応答)、通話録音など
- 特徴: 固定電話が持つ「代表番号」や「内線」といったビジネスに必要な機能を維持しつつ、場所の制約から解放される点が最大のメリットです。テレワーク環境でも、オフィスにいるのと同様の電話応対が可能になります。
IP電話 (IP Phone)
IP電話は、VoIP(Voice over Internet Protocol)技術を利用し、インターネット回線を通じて音声通話を行うサービスの総称です。クラウドPBXもIP電話の一種ですが、単体のIP電話サービスとして提供されるものもあります。
- 仕組み: 音声データをデジタル化し、パケットに分割してインターネット網で送受信します。
- 番号の種類:
- 050型: 「050」で始まる11桁の番号。全国どこでも利用でき、導入が容易で安価ですが、社会的信用度の面では市外局番に劣るとされることがあります。
- 0AB-J型: 「03」や「06」など、従来の固定電話と同じ市外局番から始まる番号。取得には一定の条件(通話品質など)があり、信頼性が高いとされています。多くのクラウドPBXサービスでは、この0AB-J型番号を利用できます。
- 特徴: 通話料が距離に関わらず全国一律で安価な点がメリットです。個人事業主や、とにかくコストを抑えたい小規模オフィスに向いています。
ビジネスチャット (Business Chat)
SlackやMicrosoft Teams、Chatworkといったビジネスチャットツールは、もはや単なるテキストメッセージのツールではありません。現代のビジネスコミュニケーションの中核を担うプラットフォームです。
- 仕組み: テキストチャットを基本に、ファイル共有、タスク管理、そして音声通話・ビデオ会議機能が統合されています。
- 主な機能: 1対1およびグループでのチャット 音声通話、ビデオ会議 各種クラウドサービスとの連携
- 特徴: 特に社内コミュニケーションにおいては、電話よりも迅速かつ記録に残るチャットが主流になりつつあります。簡単な用件であれば電話をかける必要がなくなり、全体の通話回数を削減する効果が期待できます。ただし、外部からの代表番号への着信を受けることはできません。
携帯電話の内線化
携帯キャリアが提供する法人向けサービス(FMCサービスなど)を利用して、社員のスマートフォンを内線網に組み込む方法です。
- 仕組み: キャリアのネットワークを利用して、特定の法人契約グループ内のスマートフォン同士を内線番号で呼び出せるようにします。
- 主な機能: スマートフォン間の内線通話 代表番号への着信を複数のスマートフォンで受ける(サービスによる)
- 特徴: 営業担当者など、社外での活動が多い従業員が中心の企業に適しています。クラウドPBXと機能的に重なる部分も多いですが、キャリアが提供するため通信品質の安定性が期待できる場合があります。
これらのソリューションは排他的なものではなく、多くの中小企業は「クラウドPBXを主軸に、社内連絡はビジネスチャットを併用する」といった形で、複数のツールを組み合わせて最適なコミュニケーション環境を構築しています。以下の比較表は、自社にとってどのツールが最適かを判断するための一助となるでしょう。
| 機能 | クラウドPBX | IP電話 (単体) | ビジネスチャット | 携帯電話の内線化 |
|---|---|---|---|---|
| 代表番号利用 | ◎ (可能、番号ポータビリティ対応) | 〇 (可能、0AB-J型) | × (不可) | △ (サービスによる) |
| 内線機能 | ◎ (高機能、転送・保留など) | △ (限定的、または不可) | 〇 (音声/ビデオ通話) | ◎ (可能) |
| 初期コスト | 低 | 低 | ほぼ無 | 中 (キャリア・プラン依存) |
| 場所の柔軟性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 外部ツール連携 | 〇 (CRM連携など) | × (ほぼ不可) | ◎ (多種多様なサービスと連携) | △ (限定的) |
| 最適な企業 | 外部との電話応対が多く、テレワークなど柔軟な働き方を推進したい全ての企業。 | 個人事業主や、コストを最優先し、限定的な電話機能で十分な小規模オフィス。 | 社内コミュニケーションが中心で、電話よりもテキストベースのやり取りが多いIT・クリエイティブ系企業。 | 営業職など、外出が多い従業員が中心で、キャリアのサービスで完結させたい企業。 |
中小企業の最適解「クラウドPBX」徹底解説
前章で紹介した代替ソリューションの中でも、クラウドPBXは多くの中小企業にとって最もバランスの取れた「最適解」と言えます。なぜなら、従来の固定電話が持っていた「社会的信用(市外局番付きの代表番号)」と「ビジネス機能(内線・転送)」を維持しながら、現代のビジネスに不可欠な「コスト削減」「場所の柔軟性」「拡張性」を同時に実現できるからです。この章では、クラウドPBXの仕組みからコスト、そして多くの経営者が懸念するセキュリティや通話品質について、深く掘り下げて解説します。
仕組みとメリット
クラウドPBXの仕組みは非常にシンプルです。これまでオフィス内に物理的に設置していた箱型のPBX装置が、サービス提供事業者の運用する安全なデータセンター内のサーバーに置き換わります。従業員は、手持ちのスマートフォンやPCに専用アプリをインストールするだけで、インターネットを通じてこの「クラウド上のPBX」にアクセスし、電話機能を利用します。
この仕組みにより、中小企業は以下のような多大なメリットを享受できます。
- 高額な初期投資が不要: 数十万円以上かかるPBX装置の購入や、複雑な配線工事が不要なため、初期費用を劇的に抑えることができます。これにより、貴重な経営資源を他の成長分野へ投資することが可能になります。
- 運用・管理の手間を削減: 機器のメンテナンスや保守はすべてサービス提供事業者が行うため、専門知識を持つIT担当者がいない中小企業でも安心して利用できます。設定変更などもWebの管理画面から簡単に行えます。
- 事業規模に合わせた柔軟な拡張・縮小: 従業員の増減や拠点の新設・閉鎖に合わせて、アカウント(ID)を追加・削除するだけで、電話回線の数を柔軟に変更できます。繁忙期だけ一時的に回線を増やすといった運用も可能です。このスケーラビリティは、変化の速い現代のビジネス環境において大きな強みとなります。
- 働き方改革の推進: 従業員はどこにいても会社の代表番号で電話を受け、内線で同僚と連絡を取ることができます。これにより、完全なテレワークやフリーアドレスといった柔軟な働き方が可能になり、従業員の生産性向上と満足度向上に貢献します。実際に、テレワークの定着をきっかけにクラウドPBXを導入し、在宅勤務でもオフィスと変わらない電話環境を構築した事例は数多く報告されています。
コスト分析:従来のビジネスフォンとの比較
クラウドPBXがどれほどのコスト削減効果をもたらすのか、従業員10名の中小企業を例にシミュレーションしてみましょう。
【前提条件】
- 従業員数: 10名
- 必要な同時通話数: 3チャネル
- 利用期間: 5年間
【従来のビジネスフォン(オンプレミス型PBX)の場合】
- 初期費用: PBX主装置購入費: 約300,000円 ビジネスフォン電話機 (10台): 約150,000円 設置・配線工事費: 約100,000円 合計: 約550,000円
- 月額費用: ISDN回線基本料 (3チャネル相当): 約3,500円 保守・メンテナンス費用: 約5,000円 合計: 約8,500円
- 5年間の総コスト: 550,000円 + (8,500円 × 60ヶ月) = 1,060,000円 (+別途通話料)
【クラウドPBXの場合】
- 初期費用: 初期設定費用: 約30,000円 合計: 約30,000円
- 月額費用: 基本料金 (3チャネル含む): 約3,000円 ID利用料 (10名分): 約3,000円 (1ID 300円と仮定) 合計: 約6,000円
- 5年間の総コスト: 30,000円 + (6,000円 × 60ヶ月) = 390,000円 (+別途通話料)
このシミュレーションでは、5年間で約670,000円ものコスト削減が見込めます。PBXの法定耐用年数が6年であることを考えると、機器の買い替えサイクルも含めれば、その差はさらに広がります。これはあくまで一例ですが、クラウドPBXが中小企業のキャッシュフローに与えるポジティブな影響は計り知れません。
懸念点の解消:セキュリティと通話品質
コストや利便性のメリットは理解できても、「会社の重要な通話をインターネットに乗せるのは不安」「音質が悪くて仕事にならないのでは?」といった懸念を持つ経営者は少なくありません。しかし、これらの懸念は現代の技術によって大部分が解消されています。
セキュリティ
クラウドPBXのセキュリティは、サービス提供事業者(ベンダー)側の対策と、利用者(ユーザー)側の対策の両輪で成り立っています。
- ベンダー側の対策: 信頼できるベンダーは、金融機関レベルの堅牢なデータセンターでサービスを運用しています。具体的には、24時間365日の監視体制、不正アクセスを防ぐファイアウォール、通信データの暗号化(TLS/SRTP)、サーバーの冗長化など、多層的なセキュリティ対策を講じています。むしろ、自社でサーバーを管理するよりも高度なセキュリティ環境を享受できると言えます。
- ユーザー側の対策: 利用者側でも、基本的なセキュリティ対策を徹底することが重要です。
- 強固なパスワード設定と定期的変更: 推測されにくい複雑なパスワードを設定し、定期的に変更する。
- アクセス権限の適切な管理: 従業員の役職に応じて、管理画面へのアクセス権限などを適切に設定する。
- 安全なネットワーク利用: 公共のフリーWi-Fiなど、安全性の確認できないネットワークからの利用を避けるといった社内ルールを策定し、周知徹底することが求められます。
通話品質
「IP電話は音質が悪い」というイメージは、技術が未熟だった一昔前のものです。現在、総務省はIP電話の通話品質を客観的な指標(R値)に基づき、以下の3つのクラスに分類しています。
- クラスA: 固定電話と同等の最高品質
- クラスB: 一般的な携帯電話と同等の品質
- クラスC: 上記より劣る品質
現在、法人向けに提供されている主要なクラウドPBXサービスの多くは、最も品質の高い「クラスA」の基準を満たしています。これは、ビジネス上のコミュニケーションにおいて、従来の固定電話と遜色のないクリアな音声で通話できることを意味します。
ただし、通話品質は利用するインターネット回線の速度や安定性にも影響されます。快適な利用のためには、安定した光回線などのブロードバンド環境を確保することが前提となりますが、これは現代のオフィスでは標準的な設備と言えるでしょう。
クラウドPBXは、単なる電話の代替品ではありません。通話履歴のデータ分析やCRM(顧客管理システム)との連携機能などを活用すれば、顧客対応の品質向上や営業活動の効率化に繋がる「ビジネスインテリジェンスツール」としての側面も持っています。どの顧客から、いつ、どれくらいの頻度で電話があるのかを可視化し、分析することで、人員配置の最適化やマーケティング施策の効果測定にも役立てることができます。このように、クラウドPBXはコスト削減と業務効率化を実現しつつ、企業のデータ活用を促進する、まさに中小企業のDXを加速させるための強力なエンジンとなり得るのです。
固定電話・電話回線に関する
お悩み・ご相談はお気軽に!
お客様の様々なニーズにお応えし、
ご利用に合う最適なプランをご提案します。
失敗しない!固定電話から新システムへの移行実践マニュアル
固定電話の廃止と新システムへの移行は、計画的に進めることで、業務への影響を最小限に抑えつつスムーズに完了できます。ここでは、特に重要な3つのステップ「番号ポータビリティ」「関係者への告知」「FAX業務の継続」に焦点を当て、具体的な手順と注意点を解説します。
ステップ1:会社の電話番号を維持する「番号ポータビリティ」の手続き
多くの中小企業にとって、長年使用してきた会社の電話番号は、顧客や取引先との繋がりを維持するための重要な資産です。この番号を変更せずに新しいサービスへ移行するために利用するのが「番号ポータビリティ(LNP: Local Number Portability)」制度です。
番号ポータビリティとは?
現在利用している固定電話番号を、他の通信事業者のサービス(クラウドPBXやひかり電話など)でも継続して利用できる仕組みです。
手続きの重要ポイントと流れ
番号ポータビリティを成功させるために、絶対に守るべき鉄則があります。それは「新しいサービスの開通前に、現在の電話サービスを絶対に解約しないこと」です。先に解約してしまうと、電話番号そのものが消滅し、引き継ぎができなくなってしまいます。
【基本的な手続きの流れ】
- 移行先のサービスを選定・契約: 導入したいクラウドPBXなどのサービス事業者を選び、申し込みを行います。その際、必ず「番号ポータビリティを利用したい」旨を伝えます。
- 事業者間での手続き: 申し込みを受けた新しいサービス事業者が、現在のサービス事業者との間で番号引き継ぎの手続きを代行してくれます。利用者側で複雑な作業はほとんどありません。
- 開通工事・設定: 新しいサービス(光回線など)の開通工事が必要な場合は、日程を調整して実施します。
- 新サービスの利用開始: 新しいサービスで、今までの電話番号が使えるようになったことを確認します。
- 旧サービスの自動解約: 番号ポータビリティが完了すると、多くの場合、以前の電話サービスは自動的に解約扱いとなります。念のため、旧事業者への確認を行うとより確実です。
注意点
- 引き継ぎ可能な番号: 番号ポータビリティが可能なのは、基本的にNTT東日本・西日本が発番したアナログ回線やISDN回線の番号です。一部のIP電話サービスで独自に発番された番号などは、引き継げない場合があります。事前にNTTの「116」番に電話するなどして、自社の番号がNTT発番であるかを確認しておきましょう。
- 移転を伴う場合: オフィスの移転先が現在のNTT収容局の管轄外(多くは市区町村をまたぐ場合)になる場合は、番号ポータビリティを利用できません。移転を計画している場合は、事前に移転先で番号が維持できるかを確認することが不可欠です。
- 費用: 番号ポータビリティの手続きには、手数料や工事費が発生する場合があります。具体的な金額は事業者によって異なるため、事前に確認しましょう。
ステップ2:取引先や顧客への告知と手続き
電話システムの変更は社内だけの問題ではありません。顧客や取引先に混乱を与えないよう、丁寧な事前告知と、関連する各種情報の更新が不可欠です。
関係者への告知
電話番号が変わらない場合でも、「電話システムが新しくなり、今後は担当者のスマートフォンに直接繋がるようになります」といった案内をすることで、よりスムーズなコミュニケーションに繋がります。電話番号が変更になる場合は、最低でも1〜2ヶ月前から告知を開始するのが望ましいでしょう。
【告知文の例(メール・Webサイト用)】
件名:【重要】電話システム変更のお知らせ(株式会社〇〇)
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では業務効率化および多様な働き方の推進を目的としまして、来る〇〇年〇月〇日をもちまして、従来の固定電話システムを廃止し、クラウド型の電話システムへ移行する運びとなりました。
これにより、今後は担当者がオフィス不在時でも、これまで通り会社の代表番号(XX-XXXX-XXXX)にて直接お電話をお受けすることが可能となります。
お取引様及び関係者の皆様には、より迅速かつ柔軟な対応が可能となりますので、何卒ご理解ご協力いただけますようお願い申し上げます。
なお、代表電話番号およびFAX番号に変更はございません。
敬具
各種情報の更新
電話番号が記載されている全ての媒体や登録情報をリストアップし、漏れなく変更作業を行います。
【更新作業チェックリスト】
- Webサイト: 会社概要、お問い合わせページ、フッターなど
- 名刺・会社案内・封筒: 全従業員の名刺、パンフレット類
- 各種Webサービス: Googleビジネスプロフィール、業界ポータルサイト、SNSアカウントなど
- 金融機関: 取引銀行の登録情報
- 法務・行政: 税務署、社会保険事務所などへの届出(必須ではない場合も多いが確認を推奨)
- 契約書類: 各種契約書式のテンプレート
ステップ3:FAX業務の継続方法
固定電話回線を廃止すると、それに接続されていた物理的なFAX機は使えなくなります。しかし、FAX文化が根強く残る日本のビジネスシーンにおいて、FAXを完全に廃止するのは難しい場合も多いでしょう。その解決策が「インターネットFAX」です。
インターネットFAXとは?
PCやスマートフォンを使い、インターネット経由でFAXの送受信ができるサービスです。メールを送るような感覚でPDFファイルをFAXとして送信したり、受信したFAXをPDFファイルとしてメールで受け取ったりできます。
メリット
- ペーパーレス化: FAXのために紙を印刷する必要がなくなり、コスト削減と環境負荷の軽減に繋がります。
- 場所を選ばない: 外出先やテレワーク中の自宅からでも、PCやスマホでFAXの確認・送信が可能です。
- 管理が容易: 受信したFAXはデータとして保存されるため、ファイリングの手間が省け、検索も容易になります。
サービス選定と料金
多くの事業者がインターネットFAXサービスを提供しており、料金体系は様々です。自社の送受信枚数に合わせて、最適なプランを選ぶことが重要です。
【主要インターネットFAXサービス料金比較(目安)】
| サービス名 | 初期費用 | 月額料金 | 無料送受信枚数(月) | 超過料金(1枚あたり) |
|---|---|---|---|---|
| eFax | 1,100円 | 1,980円 | 送信150枚、受信150枚 | 11円 |
| jFax | 1,100円 | 1,089円 | 送信50枚、受信100枚 | 11円 |
| MOVFAX | 1,100円 | 1,078円 | 受信1,000枚 | 送信: 8.8円、受信: 8.8円 |
| faximo | 1,188円 | 1,188円 | 受信1,000枚 | 送信: 15.4円、受信: 9.9円 |
これらのステップを一つひとつ着実に実行することで、固定電話からの移行に伴うリスクを管理し、新しいコミュニケーション環境へと円滑に移行することが可能です。
【参考サイト】https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/tel_number/kotei_portability.html
よくある質問と回答(Q&A)
固定電話の廃止を検討する際に、多くの中小企業の経営者や担当者が抱く共通の疑問や不安があります。ここでは、特に頻繁に寄せられる5つの質問に対して、具体的かつ明確な回答を提示します。
Q1. 固定電話をなくすと、銀行の融資や役所の手続きで本当に不利になりますか?
A1. かつては、固定電話の有無が事業の実在性を示す重要な指標とされ、金融機関の融資審査や公的な手続きで不利に働く可能性があったのは事実です。しかし、働き方や通信技術が大きく変化した現在、その状況は変わりつつあります。
重要なのは「携帯電話番号しかない」状態を避けることです。クラウドPBXを導入し、「番号ポータビリティ」制度を利用して既存の市外局番付き電話番号(0AB-J番号)を継続利用する場合、多くの金融機関や公的機関はこれを正規の事業用連絡先として認めます。なぜなら、審査する側が確認したいのは「事業の実態があり、確実に連絡が取れるか」という点であり、その証明として市外局番付きの番号が有効だからです。通信の手段がアナログ回線かIP回線かは、もはや本質的な問題ではありません。
ただし、金融機関や手続きの種類によっては、依然として古い慣習が残っている可能性もゼロではありません。重要な取引を控えている場合は、事前に取引先の金融機関などに確認しておくと、より安心して移行を進めることができます。
Q2. 今使っている会社の電話番号は、本当にそのまま使えますか?
A2. はい、多くの場合でそのまま利用可能です。これを実現するのが「番号ポータビリティ(LNP)」制度です。
ただし、いくつかの条件があります。最も重要なのは、その電話番号がもともとNTT東日本・西日本で発番されたアナログ回線またはISDN回線の番号であることです。過去にひかり電話や他のIP電話サービスへ移行した際に新規で取得した番号など、一部の番号は引き継げない場合があります。
自社の番号が引き継ぎ可能かどうかわからない場合は、契約しているクラウドPBXの事業者に問い合わせれば、調査してもらうことができます。繰り返しになりますが、番号ポータビリティの手続きが完了する前に現在の回線を解約してしまうと番号が失効してしまうため、絶対に避けてください。
Q3. クラウドPBXの通話品質は、固定電話と比べて問題ありませんか?
A3. はい、信頼できる法人向けサービスを選べば、品質に問題はありません。
「IP電話は音質が悪い」というイメージは、インターネット回線が遅く、技術も未熟だった過去のものです。現在、総務省はIP電話の品質を3段階(クラスA、B、C)で定めており、クラスAは「固定電話と同等の品質」とされています。
現在提供されている主要な法人向けクラウドPBXサービスは、このクラスAの基準をクリアしているものがほとんどです。したがって、業務上の通話において、音声が聞き取りにくい、途切れるといったストレスを感じることは基本的にありません。
ただし、クラウドPBXの通話品質は、利用するインターネット回線の品質に依存します。安定した通話のためには、オフィスに法人向けの光回線など、安定的で十分な帯域を持つインターネット環境を整備することが前提となります。
Q4. 導入までにかかる期間と費用はどれくらいですか?
A4. 期間と費用は、企業の規模や選択するプランによって異なりますが、小規模な企業の場合の目安は以下の通りです。
- 導入期間: 新規で電話番号を取得する場合: 最短で数営業日〜1週間程度で利用開始できるサービスが多いです。
- 番号ポータビリティを利用する場合: 事業者間の調整が必要なため、申し込みから開通まで2週間〜1ヶ月程度を見ておくとよいでしょう。
- 費用:
- 初期費用: 多くのサービスで10,000円〜50,000円程度です。キャンペーンなどで無料になる場合もあります。
- 月額費用(従業員10名の場合の目安): 基本料金とID利用料を合わせて、月額5,000円〜15,000円程度が一般的な価格帯です。これに加えて、外線通話料が別途かかります。
従来のビジネスフォン導入にかかる数十万円の初期費用と比較すると、導入のハードルが格段に低いことがわかります。
Q5. セキュリティは本当に安全ですか?情報漏洩のリスクは?
A5. はい、適切なサービスを選び、正しく運用すれば、セキュリティは非常に高いレベルで確保できます。
クラウドPBXのセキュリティは、サービス提供事業者と利用企業の双方の対策によって担保されます。
- サービス提供事業者の対策: 信頼できる事業者は、金融機関も利用するような堅牢なデータセンターでシステムを運用しています。通信の暗号化、不正アクセス検知システム、24時間365日の監視体制など、高度なセキュリティ対策を講じており、外部からの攻撃によって容易に情報が漏洩するリスクは極めて低いです。
- 利用企業側の対策: むしろ注意すべきは、従業員による意図しない情報漏洩です。例えば、顧客の連絡先が入った個人のスマートフォンを業務で無管理に使用する(BYOD)方が、端末の紛失やウイルス感染時のリスクは高まります。クラウドPBXでは、電話帳データをクラウド上で一元管理するため、端末自体に顧客情報を保存する必要がなく、万が一スマートフォンを紛失しても情報漏洩のリスクを低減できます。
企業としては、推測されにくいパスワードの設定を徹底する、公共のフリーWi-Fiでの利用を禁止するなど、明確な利用ルールを定めて従業員に周知することが、安全な運用には不可欠です。
まとめ:未来を見据えた電話環境へ、固定電話廃止で実現する新しい働き方
本記事では、総務省などの公的データを基に、固定電話を取り巻く環境が構造的に、そして不可逆的に変化している事実を明らかにしてきました。固定電話の契約数は減少し続け、一方でスマートフォンの普及率はほぼ100%に達しています。このデータは、コミュニケーションの主役が完全にモバイルへと移行したことを示しており、企業もこの大きな潮流に適応していく必要があります。
中小企業にとって、固定電話の廃止は単なるコスト削減策にとどまりません。それは、企業の未来を形作るための戦略的な一手です。
- コスト構造の変革: 高額な設備投資や維持費といった固定費から解放され、事業規模に応じて柔軟に変動させられる利用料ベースのコスト構造へ転換できます。これにより、経営の健全性と俊敏性が向上します。
- 業務効率の最大化: 電話の取次ぎといった非生産的な業務を撲滅し、従業員が本来の価値創造業務に集中できる環境を構築します。迅速な顧客対応は、そのまま企業の競争力に繋がります。
- 新しい働き方の実現: テレワーク、ハイブリッドワーク、フリーアドレスといった現代的な働き方を阻害する物理的な制約を取り払い、多様な人材が活躍できる魅力的な職場環境を提供します。これは、人材獲得競争が激化する現代において、企業の持続的な成長を支える基盤となります。
もちろん、社会的信用の維持やFAX業務の継続、災害時の備えといった課題も存在します。しかし、本記事で詳述したように、「番号ポータビリティ」を活用したクラウドPBXの導入やインターネットFAXへの移行といった現代的なソリューションによって、これらの課題は克服可能です。もはやデメリットは乗り越えられない障壁ではなく、計画的に対処すべき「移行プロセスの一部」に過ぎません。
今、皆様の会社にある電話システムは、未来の事業成長を支えるための最適なツールでしょうか。それとも、過去の慣習に縛られ、変化への足かせとなっていないでしょうか。
固定電話の廃止は、単に古いものを捨てる行為ではありません。それは、未来を見据え、より柔軟で、より効率的で、より強靭な事業基盤を構築するための、積極的な投資です。このガイドが、貴社にとって最適なコミュニケーション戦略を策定し、新しい時代の働き方へと踏み出すための一助となれば幸いです。
※本記事の情報は2025年10月に調査したものです。最新の情報などは、各省庁や公式サービス等でご確認ください。
固定電話・電話回線に関する
お悩み・ご相談はお気軽に!
お客様の様々なニーズにお応えし、
ご利用に合う最適なプランをご提案します。